|
|
|
|
 |
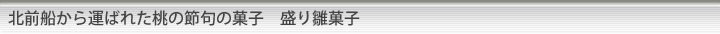 |
 |
始まりは江戸中期から明治の初めにかけての北前船による交易で、京都からひな祭りに飾られる盛り雛菓子の文化がここ山形県庄内地方の菓子職人に伝わりました。江戸時代、上級武士や豪商などの桃の節句では、お膳の上に桃や鯛、海老や藤など成長を願う縁起物などを模った落雁や飴が盛られ、ひな壇に供えて子供の成長を祝いました。
明治時代以降はひな祭りで盛り雛菓子を飾る事が庶民化し、一般の方たちもお膳に成長を祝う縁起物や地元の魚や果物を模った干菓子や飴、練り切りなどを盛った物をひな壇に飾るようになり、お菓子屋さんにはお膳一盛りではなく、二盛りを注文して煌びやかに飾り、美しさや華やかさを演出して盛大にお祝いをしました。
戦後は、スーパーマーケットに練り切りなどのパック詰めの盛り雛菓子が商品化され売り出されるようになり、より山形県庄内地方の独自文化として進化し、在地化して地域に定着していきました。 |
|
 |
|
 |
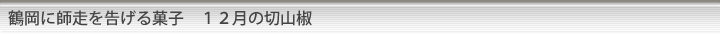 |
 |
明治も晩年の頃、地元の菓子屋の老舗長崎屋の主人佐藤甚右ェ門が友と二人でお伊勢参りに行った帰りの東京浅草見物の際、仲見世において切山椒を発見しました。佐藤甚右ェ門は前から菓子を作る際にでる多量の屑を捨てるのをもったいないと思い、これをヒントに再生することを考えつきました。屑を夏に屋根の物干し台で乾かしこれを茶箱で保存し、冬なってからこれを乾燥機にかけ石臼でひいて粉にする。それをこねて黒砂糖と山椒の粉を入れ、細く長く切って菓子に仕上げる。これが鶴岡の切山椒のルーツとなりました。
このお菓子は年の暮れの観音堂の御歳夜(通称だるま祭り)で、山椒が入っている事で冬はカゼをひかず丈夫な体で生き、細く長く切られている事で末永く生きていけると、健康と一年の無事を祈願されたお菓子として売り出されました。
現在は餅米を炒り蒸かし、臼でつき、黒砂糖と山椒を入れる作り方に変わりましたが、今でも観音堂の御歳夜でダルマと一緒に縁起物として売られています。 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|